Googleの強力なAIモデル「Gemini」がターミナル(端末)から直接使えるようになりました。それがGmini CLIです。
早速Linux, Mac, Windowsで使ってみています。
さて、なぜ今、Gemini CLIなのでしょうか?
ChatGPTなどのWebサービスは便利なのですが、開発者や多くのLinuxユーザーにとって、ターミナルから直接AIを操作できるのは非常に大きなメリットとなるわけです。なるべくマウスは使わずにキーボードだけで操作をしたいので。。。
手軽さ、そして既存の作業環境とのシームレスな連携は、一度使うと手放せなくなるかもしれません。
Linux MintでのGemini CLIセットアップ手順
1. Node.jsの管理ツール「nvm」をインストール
Gemini CLIは、現在Node.jsというJavaScriptの実行環境上で動作させる方法が主流となっています。
まずは、Node.jsのバージョンを管理するためのツールである「nvm」を追加します。
- nvmの最新版のバージョン番号を確認するために、GitHubリリースページにアクセスします。 https://github.com/nvm-sh/nvm/releases
- 一番上に表示されているバージョンが最新版です。 例えば、
v0.40.3のように表示されています。 - 下記のコマンドのバージョン番号を最新のものに置き換えて実行します。
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash2,設定の読み込み
インストール後、端末をいったん閉じて再度立ち上げるか、次のコマンドを実行してnvmを有効にします。
source ~/.bashrc3,インストール確認
以下のコマンドでnvmのバージョンが表示されれば、正常にインストールされています。
nvm --version4,最新のNode.jsとnpmのインストール
次に、nvmを使って最新のLTS(Long Term Support – 長期サポート版)のNode.jsをインストールします。npmはNode.jsに付属しているため、同時にインストールされます。
Node.jsのインストール: 以下のコマンドを実行して、最新のLTS版Node.jsをインストールし、デフォルトとして設定します。
nvm install --lts
nvm use --lts
nvm alias default 'lts/*'インストール確認: 以下のコマンドで、それぞれのバージョンが表示されることを確認します。
node -v
npm -v5,Gemini CLIのインストールとセットアップ
最後に、npmを使ってGemini CLIをインストールし、初期設定を行います。
Gemini CLIのインストール: 以下のコマンドを実行して、Gemini CLIをグローバルにインストールします。
npm install -g @google/gemini-cliインストールが完了したら、次のコマンドでバージョンを確認。表示されたらOKです。
gemini --version起動します。
geminiテーマの選択画面が現れます。上下キーで好みのものを選択します。

6,Gemini CLIの認証(ログイン)
Gemini CLIを使うには、GoogleのAIサービスへの認証が必要です。Googleアカウントでログインします。

ブラウザーが自動で開いてGoogleアカウントの認証が行われます。許可をして進めます。
Gemini CLIで何ができるの?どこがすごいの?
Gemini CLIは単なるチャットボットではありません。その強力な機能と「すごい」点は多岐にわたります。
Gemini CLIでは何ができるの?・・・このようにプロンプトで入力すれば教えてくれます
1. AIとの自由な対話(REPLモード)
ターミナルでgemini と入力するだけで、Gemini CLIが起動し対話モードに入ります。
質問をしたり、アイデア出しをしたり、情報収集をしたりと、まるでAIと会話をする感じで使えます。
「Pythonのクラスについて簡単に説明して」を伝えると、例え話を交えながら教えてくれます。

2. プログラムコードの生成
プログラマーにとっては特に強力な機能となります。
例えば 「Pythonでフィボナッチ数列を生成する関数を書いて」といった指示でコードスニペットを生成できます。

3.プログラムコードのデバッグ・リファクタリング

ファイルやディレクトリを指定して命令をする場合、@ コマンドを使って、ローカルのファイルやディレクトリの内容をAIの参照情報として渡すことができます。ファイル名に「*」をつけることで、以下省略となります。

軽微なバグを修正してくれました。ありがたいことです。
または、「このコードをもっと効率的にリファクタリングして@count*」とすれば、より洗練されたコードに書き換えてくれるわけですね。
いやぁ、ホントに心強いです。
4. ローカルのファイル内容を理解させる
@ で、ローカルのファイルやディレクトリの内容をAIの参照情報として渡すことができます。

2万文字あるホワイトペーパーの要点を完結にまとめてもらいます。指定したファイル(今回はPDFファイル)の内容をいったん理解した上で回答してくれます。

プロジェクトの全体像をAIに理解させたり、特定のコードファイルを分析させたりする際に「@」での指定はとても役立ちそうです。
5. Web検索機能との連携
GeminiはWeb検索機能と連携できるため、常に最新の情報に基づいて回答を生成できます。従来のAIモデルが苦手としていた「学習データにはない最新情報」にも対応できるため、情報収集の幅が格段に広がります。

この問に対して、Web を検索した上でまとめてくれます。

このように、コード生成だけでなく、テキストの要約、翻訳、クリエイティブな文章の生成など、多岐にわたるタスクに対応します。さらに、将来的には外部ツールとの連携も強化され、ワークフローに深く統合されていくことでしょう。とても楽しみです。
コンピューターの操作
Gemini CLIに「音量を0にして」のようなPCの操作をお願いすると、許可を求められます。「allow once」にしておけば毎回、確認が出るので安心ですね。

承認すると、Geminiモデルがその指示を理解し、パソコンでその操作を実行するためのシェルスクリプトを生成して対応してくれます。

これは、以下のような仕組みで動作しています。
- ユーザーが指示を出す: ユーザーがGemini CLIに「パソコンの音量を0にして」と自然言語で入力します。
- Geminiモデルが解釈・コード生成: Geminiモデルがその言語を解釈し、「パソコンの音量を0にする」という操作を実行するための最適なスクリプトを生成します。
- CLIがコードを提示・確認: Gemini CLIは、生成されたスクリプトをユーザーに提示し、「このコマンドを実行しますか?」というように実行の確認を求めます。
- ユーザーが承認・実行: ユーザーが承認すると、CLIがそのスクリプトをPCのターミナル(端末)で実行し、実際に音量が0になります。
なぜこのような仕組みなのか?
これはセキュリティと透明性のためです。
- セキュリティ: Gemini自体はクラウド上で動作しているAIであり、勝手にユーザーのPCを操作することはできません。もしAIが自由にPCを操作できると、重大なセキュリティリスクになってしまいます。
- 透明性: 実行前に必ずスクリプトの内容をユーザーに提示することで、どのような命令が実行されるのかをユーザー自身が確認・管理できます。これにより、意図しない操作が行われるのを防いでいるんですね。
Gemini CLIをどう活用する?
私が思いつく限りになってしまいますが、次のようにつかえるなぁ!と実感しています。
活用アイデア1:プログラミングの強力な味方に!
- 簡単なコードスニペットを生成: 「JavaScriptで配列をシャッフルする関数を書いて」
- エラーの解決を手伝ってもらう: プログラミング中に発生したエラーメッセージをコピーして gemini “このエラーは何?どうすれば直せる?” と質問
- 基本概念の言語化 「Pythonのクラスについて初心者にどのように教えればいい?」のように、プログラミングの基本概念をわかりやすく表現してもらえます。
活用アイデア2:文書作成や情報収集を効率化!
- 要約ツールとして: 長い記事やドキュメントを読み込む時間がない時、ファイルパスを指定して gemini “このレポートを500字で要約して:@report.pdf” のように(上述の通り)。
- ブレインストーミングの相手に: 「ブログ記事のアイデアを5つ提案して。テーマはLinux Mintの便利機能」といったプロンプトで、アイディアを引き出すことができますね。
- 調べもの: WikipediaやWebサイトを検索する代わりに、gemini “Linux Mint 23のリリース日はいつ?” のように質問すれば、AIがWeb検索して回答してくれます。
活用アイデア3:Linuxコマンドのヘルプ!
- コマンドの使い方を質問: 「grep コマンドでファイルから特定の文字列を検索する方法を教えて」といった質問で、コマンドの使い方を学べます。
- シェルスクリプトの作成支援: 「ホームディレクトリのファイルをバックアップするシンプルなシェルスクリプトを書いて」と頼んでみれば、基本的なスクリプトを生成してくれます。
まとめ:ターミナルからAIの力を引き出せる
Gemini CLIを導入することで、パソコンのターミナルが単なるコマンド入力画面から、AIの力を直接引き出せる強力なワークステーションへとパワーアップしました。
プログラミング、執筆、情報収集など、様々な場面でGUIとうまく使い分けながら、生産性を高めてくれそうです。
コラム:なぜGeminiにCLI(コマンドライン・インターフェース)?
GeminiにCLI(コマンドライン・インターフェース)バージョンが存在するのは、主に開発者やパワーユーザーの特定のニーズに応えるためなんでしょうね。GUIにはない、CLIならではの強力な利点がいくつかあります。
- 連携と自動化 (Integration & Automation) これが最大の理由だと思います。CLIは他のコマンドやスクリプトと簡単に組み合わせることができますし。
- スクリプト化: 「特定のファイル群を検索し、その内容をGeminiに要約させて、結果をファイルに出力する」といった一連の作業を自動化するスクリプトを組むことができます。GUIではこのような自動化は困難です。
- CI/CDパイプラインへの統合: 開発プロセス(CI/CD)の中にGeminiを組み込めます。例えば、「コードがコミットされたら、自動でGeminiがコードレビューを行う」といったワークフローも実現できそうです。
- 速度と効率性:熟練したユーザーにとっては、キーボードから手を離さずにすべての操作を完結できるCLIの方が、マウスであちこちをクリックするGUIよりも高速に作業できるのです。
- 開発環境へのシームレスな統合: 開発者の多くは、日常的にターミナル(黒い画面)でgit、docker、npmといったコマンドラインツールを使って作業しています。GeminiのCLIは、彼らが普段作業しているその環境に直接統合されるため、ブラウザや別のアプリに切り替える必要がなく、思考を中断させずに作業を続けられます。
- パワフルさと柔軟性:CLIは、コマンドの出力を別のコマンドの入力として渡す「パイプ” | “」という機能を使えます。これにより、非常に柔軟でパワフルな操作が可能になります。 (例)ls -1 *.js | gemini “このJavaScriptファイルリストの概要を教えて”
- SSH経由での利用: サーバーなどにSSHでリモート接続して作業している場合、GUIは利用できません。CLIツールなら、そうした環境でも問題なく動作します。
車に例えるなら、GUIが誰でも運転しやすいオートマ車だとすれば、CLIはより細かい操作や高いパフォーマンスを引き出せるマニュアル車のような位置づけと言えるかもしれません。両方にはそれぞれの良さがあり、用途によって最適な方が選ばれる、ということなのかなぁ、と思っています。




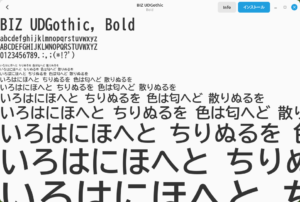


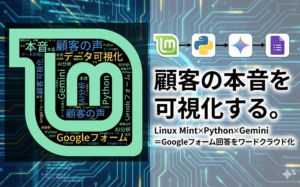


コメント