論文作成は複雑なプロセスですが、AIの進化はこれを劇的に効率化してくれています。AIを活用し、いくつかのツールを組み合わせることで、文献調査からデータ分析、執筆、推敲に至るまで、全工程を効率良く進めていくことが可能になってきています。
例えば、AIは文献調査で関連論文を素早く抽出し、要約することで効率的な情報収集を可能にします。
データ分析では、複雑な統計処理を支援し、深い洞察を導き出します。
執筆段階では、文法チェックや表現提案、引用形式の調整を自動で行い、執筆者が内容に集中できるようサポートします。
これにより、論文作成にかかる時間とストレスが軽減され、研究者はより質の高い論文を効率的に完成させることができます。AIは、研究の質そのものの向上にも寄与する画期的なアプローチとなっています。
AIの世界は急速に進歩していますが、現時点での私なりのプロセスについてご紹介させていただきます。
ステップ1:テーマ設定と先行研究の探索
論文作成の最初の関門は、テーマの明確化と徹底的な先行研究調査です。
大まかな方向性の特定(Consensus)
研究テーマに関する疑問を具体的な質問形式でConsensusに入力します
(例:「Does mindfulness meditation reduce anxiety in university students?」)。

AIが生成する論文の要約や傾向(Consensus Meter)を参考に、テーマの現状や研究の方向性を大まかに掴みます。これにより、個々の論文を読み始める前に、全体像を把握できます。
Consensusで見つけた興味深い論文のタイトルや概要を一時的に控えておくといいですね。
研究の繋がりを可視化・キー論文の特定(Connected Papers)
Consensusで見つけた中で最も関連性の高い「キー論文」をConnected Papersに入力します。
このツールが生成する視覚的なグラフを通して、キー論文が引用している先行研究(Prior Works)と、キー論文を引用している後続研究(Derivative Works)を一目で把握できます。

グラフ内で影響力の高い(多くの繋がりを持つ)論文や、最新の研究を見つけ出し、網羅的な先行研究リストの基礎を築きます。これにより、重要な研究の見落としを防ぎます。
ステップ2:文献管理と情報整理
集めた論文情報は、効率的な管理が論文の質とスピードを左右します。
論文データベースの構築と情報の一元化(Notion)
Notionに「論文データベース」を作成し、以下の項目を含めます。
- タイトル、著者、発行年、ジャーナル/会議、DOI/URL
- タグ(研究分野、手法、キーワードなど、自由に設定)
- ステータス(未読、読み途中、読了、重要、引用済みなど)
- 概要/要約(Consensusの要約をコピペし、自分の言葉で追記)
- 主要な主張/発見、研究方法
- 自分のコメント/アイデア(論文を読んでの考察、引用箇所、今後の疑問など)

NotionのWebクリッパーを活用し、ブラウザで開いている論文の情報をワンクリックでデータベースに保存します。

私の場合、Notionのフィルターやソート機能を駆使して、必要な論文に素早くアクセスできるように整理するようにしています。
引用情報の管理と参考文献リストの準備(Zotero / Mendeley)
私にとってはNotionで十分だと思っているのですが、ZoteroやMendelyなどの文献管理ツールにも登録しておくと便利そうです。(私はまだ活用できていません)
これらのツールは、PDFの管理、ハイライトや注釈の追加、そして論文執筆時に必要な引用形式(APA, MLAなど)への自動変換と参考文献リストの自動生成を可能にしてくれます。
Notionで全体的な情報と進捗を管理し、Zotero/Mendeleyで詳細な引用情報を扱うという連携が最も効果的になりそうだと思っています。(後述の参考文献リストの作成に便利そうです)
ステップ3:論文構成の検討と執筆準備
先行研究が整理できたら、いよいよ論文の骨格を作り始めます。
NotebookLMで構成案を壁打ちしながら作成
ここで登場するのがGoogle NotebookLM。自分でアップロードした資料(ソース)だけを情報源として、的確な要約、解説、アイデア出しまでこなす、まさに「自分専用のパーソナルAIアシスタント」と言えるものです。
次のように活用しています。
- 大量の先行研究論文と共に自分でまとめた資料などを読み込ませ、研究テーマに関する要約や、重要な論点をリストアップさせる。
- 数十本の論文PDFをアップロードし、「この研究分野の最新の動向をまとめて」といった質問で、一瞬にしてレビューを完成させる。
- 自分で書いた論文の草稿も一緒にアップして共通点、相違点の洗い出しなどもすぐに分析表示してくれる。


論文アウトラインの作成(Notion)
Notionのページで、論文の「章立て」と「各章で記述すべき主要な内容」を具体的にリストアップします。
各章の項目に、先行研究データベースから関連する論文のリンクや具体的なメモを貼り付けていきます。これにより、執筆時に必要な情報にすぐにアクセスできます。
アイデアと構成の視覚的整理(MindMeister)
NotebookLMにもマインドマップ作成機能はありますが、論文の導入、各章の論点、結論など、複雑な思考やアイデアを整理する必要ばある場合、MindMeisterなどのマインドマッピングツールが便利です。
これにより、論理的な繋がりや構造を視覚的に捉え、論文全体の構成を練るのに役立ちます。

ステップ4:執筆と推敲
具体的な執筆フェーズでは、AIの力を借りて効率と質を高めます。
論文の執筆(Notion)
- Notionのアウトラインに沿って、各章のコンテンツを直接書き進めていきます。
- 自分の考察と引用したい先行研究の区別を明確にし、引用箇所にはZotero/Mendeleyのキーを記載したり、Notionのリンクを貼ったりしておくと便利そうです。
- 執筆中に生じた疑問点や、追加で調査が必要な内容は、再びConsensusやConnected Papersに戻って検索し、Notionに追記しておきます。
文章の質を高める(ChatGPT/Gemini)
- 執筆した文章は、Gemini, ChatGPTでアイデアのブレインストーミング、特定の段落の言い換え、要約の生成、論理的な飛躍がないかの確認を行います。
- 英語論文の場合、DeepL Writeを使って文法、スペル、表現の修正を行います。このDeepL Writeは、より自然でアカデミックな言い回しを提案してくれるため、英語論文の質を向上させるのにとても便利です。
図表とデータの可視化(Looker Studio)
論文に含める図や表は、GoogleのLooker Studioを用いて調査結果を可視化します。
フローチャートや概念図を作成するにはLucidchartも便利そうです。
これにより、論文の説得力を高めます。
ステップ5:最終確認と公開準備
論文の完成度を高めるための最終ステップです。
参考文献リストの生成(Zotero / Mendeley)
論文執筆には、Googleドキュメントを使用しています。
Zotero/Mendeleyのプラグインを利用することで、指定された引用スタイルに準拠した参考文献リストを自動生成することができるそうです。これにより、手作業でのミスやフォーマットの不統一を防ぐことができます。
最終的な校正と確認(Grammarly / 自己レビュー)
学術論文の盗用チェックに特化したツールとして、iThenticate (Turnitin)があり、主に学術機関や出版社、研究機関などで、論文やレポートの剽窃(盗用)チェックと、研究公正の推進のために広く活用されています。
個人利用も可能ですが、単発利用の場合1論文あたり100USドル(約15,000円弱)が目安となっています。
また、12ヶ月有効のクレジットで次のようなプランもあります。
- Single: 125ドル(論文1本、25,000語以下、5回の無料修正を含む)
- Multiple: 300ドル(論文3本まで、または1本75,000語まで、5回の無料修正を含む)
このロードマップとツールの組み合わせにより、論文作成の各段階で発生する課題を効率的にクリアし、より質の高い論文をよりスムーズに完成させることができることでしょう。


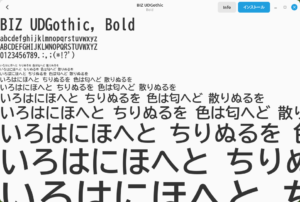


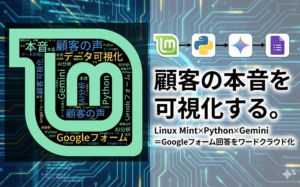




コメント